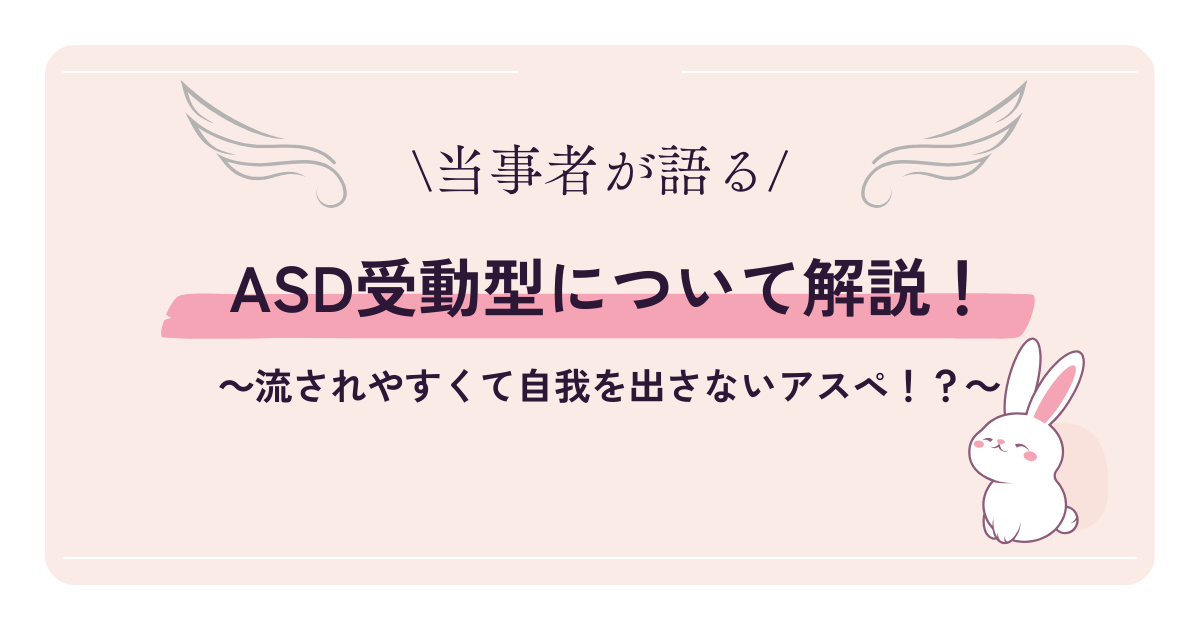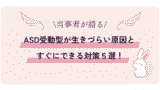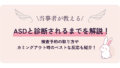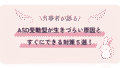こんにちは。栖山 依夜(すやま いよ)です。
私は2024年にASD(自閉症・アスペルガー)の診断を受けています。
皆さんは、ASDと聞くと最初にどんな印象を受けますか?
「空気が読めない」「冗談が通じない」「こだわりが強い」といった、コミュニケーションが難しい人のようなイメージがあるのではないでしょうか。
しかし、ASDには「受動型」といわれる「気を遣いすぎるタイプ」があります。
今回は、世間的なASDのイメージとは異なる「ASD受動型」について紹介します。
この記事を読めば、「ASD受動型」の特徴や他のASDとの違いについてわかります。
・ASDの診断を受けたが、あまりピンと来ていない
・他人に合わせすぎてしまって辛い
・無理をしすぎて精神的に疲弊してしまったことがある
・ASD受動型のことをもっと知りたい
「自身がASDかどうかわからない」「一度検査を受けてみたい」といった方には、こちらの記事もおすすめです。
ASD受動型ってどんな人?

ASD受動型は、具体的に以下のような特徴があります。
①自己表現が苦手
②流されやすい
③ASDであることが気づかれにくい
基本的に、ASD受動型は受け身なことが多く、周囲に合わせるような行動が特徴的です。
受動型の人は、「ただの大人しい人」のように思われることも多いため、発達障害であることが気づかれにくいといわれています。
また、ASD特有の「我の強さ」が目立たないため、トラブルを起こすこともほとんどありません。
これまで注目されてきたASDの特徴を踏まえると、受動型がASDだと気づかれにくいのも納得がいきますよね。
受動型は、とにかく人に合わせようと無理をすることが非常に多いです。
そのため、慣れない場所で過剰適応してしまうことも多く、二次障害が問題になりやすいといわれています。
そんな受動型さんが、生きやすくなる方法はこちらでまとめています。
ASDらしい特徴は何がある?

ASD特有の症状が目立ちにくい受動型ですが、ASDの特徴が目立つ部分もあります。
後述する「社会性の障害」と「こだわり」はその代表的な例です。
しかし、ここでも受動型はいくつか、ほかのASDと異なる特徴が出現します。
「社会性の障害」
「社会性の障害」は、簡単にいうと、周囲の状況に合わせた行動が取れないことです。
ASDでは主に、思ったことをすぐに言ってしまう、暗黙の了解が理解しづらいといった症状がよく挙げられていますよね。
しかし、受動型の症状で表れる「社会性の障害」は、一般的なASDとは少し異なる部分があります。
それが受動型の特徴でも挙げた、「自己表現の苦手さ」です。
「自己表現の苦手さ」
自己啓発本や就職活動で、「軸をしっかりと持ちましょう。」「自分の軸がブレないように!」という言葉を見かけたことはないでしょうか。
受動型の人は、基本的にこの軸が曖昧だといわれています。軸が曖昧な状態で、自分の考えを説明するのは誰でも難しいですよね。
しかし、受動型の人はその「難しい」という気持ちを周りに表現するのがとても苦手です。
その結果、周りに合わせて行動することが増え、自分の意見を発する機会がどんどん少なくなってしまうという悪循環に陥ってしまうのです。

自分の考えを話す場所は本当に苦手です…。
「全体を見る力の弱さ」
次によく表れる症状が「全体を見る力の弱さ」です。
これは受動型にかかわらず、ASD特有の特徴でよくいわれているものです。
脳の障害で、中枢性統合という部分が関係しているとされています。
中枢性統合とは全体を把握できる能力のことで,ASD者は同時に複数の情報が把握できないため,中枢性統合が弱いといわれます。
特徴として、情報の全体ではなく、細部だけを見てしまうため、この状況は「シングルフォーカス」とも言われています。
主な特徴としては、以下のような状況で症状が出やすいです。
・運転ができない
・料理ができない
・メモを取るのが難しい(何を書くべきかわからない)
・会話に入るタイミングがわからない
私の経験としては、就職活動の時が一番、ASD特性に振り回されていたように思います。
それも、人生で一番苦戦したと言っても過言ではないほど。
「自分の軸」がなかなか定まらず、書類選考で落とされ続け、良いところまでこぎつけた面接では、余計なことを言ってしまい、お祈りメール・・・なんて経験もありました。
余計な発言というのは、発達障害ではあるあるかもしれませんね。
「もっと先のことを見据えて行動すべきだった」とその時は思うのですが、他のことで頭がいっぱいいっぱいになると、いつの間にか忘れてしまい、自分を責めるということの繰り返し。
この時の私の行動は全てASD受動型の特徴に当てはまっていました。
「こだわり」
ASD受動型にも「こだわり」があるといわれています。
ASDという特性上避けられない「こだわり」ですが、ここでも受動型は他のタイプとは異なった形で表出します。
それが、こだわりを我慢してしまうという行動です。
「今、ここでこだわりを出しては周りに迷惑がかかるな」
「自分だけが我慢すれば丸く収まることだから」
と、自分の欲求よりも周囲への反応が先に表れ、とにかく我慢してしまうのです。
同じ「こだわり」という特徴でも、他のタイプがストレス発散につながるような行動を起こすのに対し、受動型は、自分の気持ちを内側に押さえ込んでしまいます。
ASDの有無にかかわらず、ストレスを溜め込み続けることは、健康にも悪影響を及ぼすといわれています。
最初は、なんとか抑えることができるのですが、この我慢が毎日続くと、今度は身体に症状が現れてきます。
私が適応障害になってしまったのは、まさにこの状態だったように思います。
そのため、ASD受動型の人は、ストレスでの二次障害には特に注意が必要になってきます。
ASD受動型の子ども時代って?

ASD受動型の子ども時代は、「大人しい子」「いい子」というふうに映ることが多いです。
私自身、ASDだと診断されたのが20代と遅めでした。
周りの人どころか、本人ですらも「ASDであること」に気づいていない可能性もあります。
ASD受動型は「いい子」に映りやすい
特に学生生活では、受動的な態度が「いい子」と捉えられやすい傾向があります。
黙って授業を聞いている生徒が、先生にとって「いい子」となるのは、想像に難くないですよね。
私も例に漏れず、小中高と「大人しい生徒」でした。
通知表には、いつも「もっと手を挙げて発表してみよう」「大きい声を出してみよう」と書かれていました。
こうした経験からも、子ども時代にASD受動型の傾向を見つけ出すのは、かなり難易度が高いのではないかと思います。
ASD受動型が生きづらくなるのは「社会人」から
私の経験上、ASD受動型の症状が顕著に出てくるのは、アルバイトや就職などの社会に出るタイミングからだと思っています。
特にASDにとって難易度が高いのは、以下のようなものです。
①臨機応変な対応
②上司・部下とのコミュニケーション
③ビジネスメールや電話の対応
④「あれ」「あの書類」「適当に置いといて」「自分で考えて」といった曖昧な言葉
ASDはイレギュラーなことが起こると、パニックになる確率が格段に高くなります。
悲しいことに、一般的に求められる社会人像と、ASDの特性はかなり相性が悪いです。
就職活動で、求められるのは常に能動的な存在なんですよね。
臨機応変な対応と、曖昧な言葉が難しいASDの人にとって、慌ただしい社会人生活はとにかく苦しいことだらけです。
特に「受動型」の人は断れない、はっきり言えないストレスがかかる状態が続きやすくなります。
そのため、ASD受動型の人は自分で自分を守ることが大切にだといえます。
具体的な原因と対策はこちらの記事でまとめています!