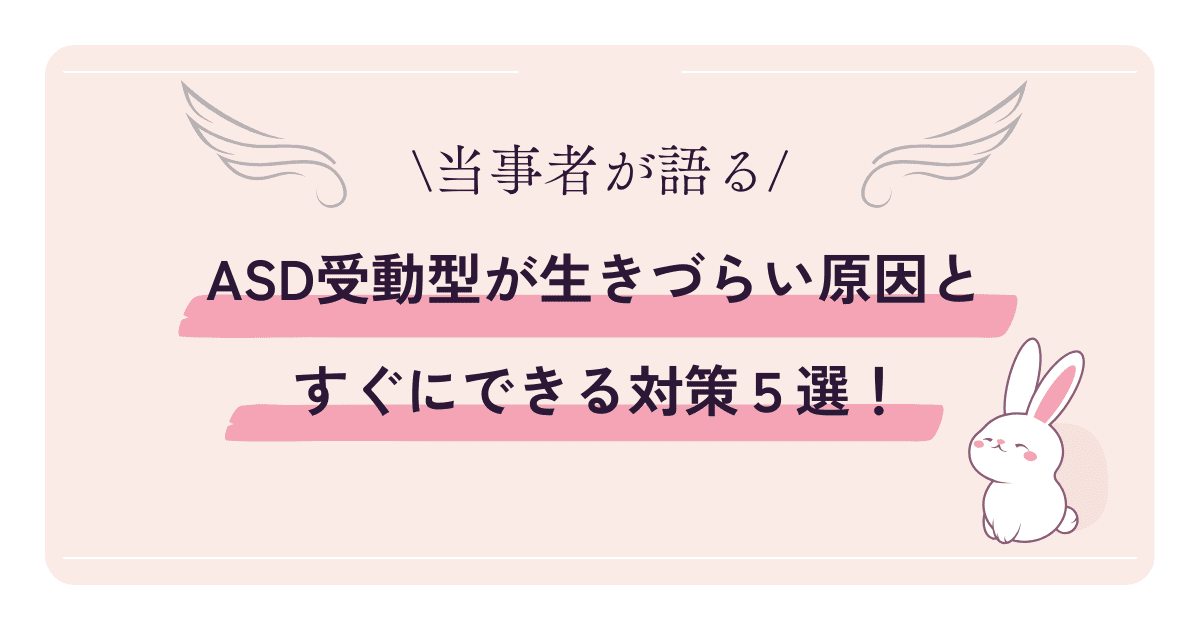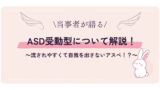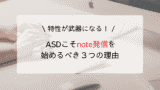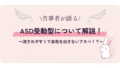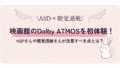こんにちは。栖山 依夜(すやま いよ)です。
私は2024年にASD(自閉症・アスペルガー)の診断を受けています。
以前、ASDの受動型というタイプについて記事をまとめました。
この記事では、ASD受動型が生きづらさを感じる原因と、対処法についてまとめています。
・「無理に人に合わせてしまう」
・「自分の意見が言えない」
といった特徴を持つASD受動型さんは、自分を大切にすることが大切です。
この記事を読めば、ASD受動型さんが生きやすくなるちょっとしたコツがわかります。
・自分はASD受動型かな?と思っている
・他人に合わせすぎてしまって辛い
・無理をしすぎて精神的に参ってしまったことがある
・ASD受動型のことをもっと知りたい
発達障害の検査を受けようか考えているという方は、こちらの記事もおすすめです。
ASD(自閉スペクトラム)には、大きく分けて、「積極奇異型」「受動型」「孤立型」の3タイプ、派生した「尊大型」「大仰型」2タイプの、計5タイプがあります。
筆者は「受動型」を自認していますが、これらは、医師から診断が下るものではありません。
タイプによって、言動や雰囲気が異なる場合も多いため、本文中の文章が必ずしも、全てのASDに当てはまるというわけではないことを、ご了承いただければと思います。
受動型が生きづらいのは「環境」が原因!?

ASD受動型の方が生きづらさを感じる原因として、「日本特有の環境」が挙げられます。
他人を変えることはほとんど不可能に近いもの。
発達障害の方はできる限り、自分が生きやすい環境を探すことが大切になってきます。
出る杭は打たれる
日本では、同調圧力が強く、出る杭は打たれることが多い環境にあります。
授業でも、仲間意識を持つことが大切だと教えられてきた方も多いと思います。
しかし、ASDの人は特性により、この日本特有の「足並みを揃える」が苦手な場合が多いです。
また、抽象的なことの理解が苦手なため、「暗黙の了解」がわかりにくいという面もあります。
そのため、ASDの人はいつの間にか周囲から孤立している、ふとした発言で浮いてしまう、普通を追い求めすぎて疲れてしまうといった状態に陥りやすいのです。
「いい人」がカモにされやすい
ASD受動型の人は、ストレスを溜め込みやすいという特徴があります。
これは感情を表に出すことが苦手な特性によるものです。
環境によっては体調を崩してしまうほどの悪影響を及ぼすことがあります。
最もわかりやすい例が、学校や会社などの集団生活です。
集団生活では足並みを揃えることに加えて、個々の意見を求められる機会が数多くあります。
社会人になると、自分で「できるもの・できないもの」を取捨選択していく必要があります。
このとき、「断れない」「意見が言えない」という特性が影響するとどうなってしまうのか。
それは、利用されてしまうということです。
ASD受動型の人は、無理をしてしまいやすいため、注意する必要があります。

「嫌われるのが怖い」「孤立したくない」という気持ちで、キャパを超えてしまいがち…
ASDの人にとって、日本の閉鎖的な環境は、かなりハードルが高いもの。
悲しいことに、日本には、ASDが生きづらい要因が揃っているのです。
私自身、本当の自分を隠して日々を過ごすのは、かなり苦しかったです。
ASD受動型が注意すべきことは何なのか?

ASD受動型の人は、優しい人、断らない人といった第一印象を持たれがちです。
そのため、周囲の人との付き合い方を考えておくことが大切になります。
特に、以下のような問題が生じやすいため、注意が必要です。
・無理をして生じたストレスによる二次障害
・利用されるリスク
・悪意ある人に騙されるリスク
私の経験上、一方的に尽くしたとしても、何も返ってこないことが多かったです。それどころか、お礼も言わずにさらに利用しようとしてくる人もいました。
・できる・許せる範囲を作る
・ある程度の範囲を超えた場合は断る
といったように、自分の基準を設けておくことが大切です。
私は、「断るための言葉」を事前に考えて断る練習をしていました。

今できることやるという方法が、私にはあっていました!
ASD受動型が生きやすくなるための5つの方法

自分を押し殺すばかりでは、いずれ精神のバランスを崩してしまいます。
それでは、どんな行動を取れば良いのでしょうか?
ここでは、「ASD受動型さんが生きやすくなる方法」を5つ紹介したいと思います。
自分と向き合ってみる
モヤモヤを言語化することが苦手なにおすすめしたいのが、ジャーナリング。
1つの質問に対して「なぜそう思うのか?」を繰り返していくと、自分でも知らなかった答えに辿り着くことがあります。
「自己分析 質問」と調べると、ネットでも質問集が出てきます。それらを活用して、ノートなどに書き出してみるのも良いでしょう。
自分と向き合うことで、「私は自分のことをよく知っている!」という自信にも繋がり、軸の安定にも繋がります。
実際に行動してみる
やりたいことや好きなことがわかってきたら、思い切って行動することをオススメします。
ASDの方は自分のペースで行動できることが、何よりも安心感に繋がります。
私の場合は、読書や散歩でも達成感を得ることができました。
慣れてきたら、次は「〜したい!」という気持ちを誰かに伝えてみることもオススメです。
成功体験を重ねていくと、自己肯定感に繋がります。
「私はできるんだ!」の気持ちを積み重ねていくことが大切です。
ストレス発散方法を見つける
ASDの特性として、脳内で思考が止まらなくなってしまうということがあります。
瞑想やヨガをしてみても、脳内がガヤガヤして全く心が落ち着かない、なんてことも。
(私は無音がダメで適度な音がないと集中できませんでした)
そのため、運動などのできるだけ頭を使わない方法を取り入れるのが大切です。
私は、一人カラオケに行ってフリータイムで歌うことが多かったです。
あまりにもストレスがひどかった時には、枕に顔を埋めて叫んだこともありました。最近では、叫ぶ専用の壺などもありますね。
やり切った後に、適度に身体が疲れるような方法を探してみると良いでしょう。
発信活動を始めてみる
数々の方法を試してきて、私が一番効果を感じたのが「発信活動」でした。
デメリットばかりが取り上げられがちなSNSですが、メリットもあります。
それは、仲間と出会えるということです。
性別や年代がバラバラな人たちと繋がることができるのがSNSの醍醐味でもあります。
本来、出会えるはずのなかった人たちと交流することで、自分の視野が広がったり、仲間がいるという自信に繋がったりといった効果があります。
応援してくれる人の存在は、生きる支えにもなります。
発信する媒体として、私がおすすめするのはnoteです。文章を書くのが好きな人が集まっているので、他のSNSと比べて平和な印象です。
ASDについて発信している方も沢山いるので、読んでいるだけでもとても勉強になります。
私も、日々発信しているので、よければ覗きに来てください。

フォロー、スキ、いつでもお待ちしています!
カウンセリングを受けてみる
なかなか上手くいかないときは、専門家の力を借りてみるのも1つの方法です。
敷居が高そうなイメージがあるかもしれませんが、全くそんなことはありません。
長年悩んでいることでも、密かに改善したいと思っていることでも、何を話しても大丈夫です。
話がまとまらなくても、泣いてしまってもOK。
私もカウンセリングを受けていましたが、かなり心が軽くなりました。
対話を通して、思考のクセやモヤモヤの原因がわかることがあります。
お金はかかりますが、学んだことは一生モノになります。
ぜひ一度検討してみてほしいです。
治すのではなく、受け入れよう

ASDは病気ではなく、生まれつきの脳の働き方の違いといわれています。
親の育て方が影響するといったことも、一切ありません。
止まり切った身長を伸ばせ!と言われて、できる人がどれだけいるでしょうか。
大金を払って、手術をすれば可能かもしれませんが、到底無理な話ですよね。
ASDも、同じなのです。
私は診断されるまで、頑張れば人並みになれるはずと思い込んで無理をしていました。
アルバイト時代は、寝る間を惜しんで復習をする生活を1年以上続けていました。
それでも、いざやってみるとパニックで頭が真っ白。入ってきて1ヶ月の後輩に教えられてしまうこともありました。
努力しても、限界というものがあります。
必要なのは、「治す努力」ではなく「受け入れて前に進む努力」です。
私はこのことに気づくまでに、7年かかってしまいました。
この記事を読んでくれたあなたが、自分を好きになれる第一歩を踏み出せることを願っています。