こんにちは。栖山 依夜(すやま いよ)です。
私は2024年にASD(自閉症・アスペルガー)の診断を受けています。
先日、発達障害をはじめとする特性や症状を持っている方を「困った人」と称した本がSNS上で炎上するという出来事が起こりました。
当事者としては、かなり心が痛む内容でした。
現在、炎上は収まっていますが、感じたことを忘れないためにも記事として残します。
2025/04/19現在 (2025/4/28 追記)
・イラストレーターは謝罪し、「ラフの大きな修正が入った」ことを明らかにしています
・著者は「差別意識は全くなかった」「(動物は)愛らしい表現」とコメント
・出版社は謝罪の一方で「本書籍をお読みいただくことでご理解いただける」とコメント
・サイトによっては注文ができない状況 注文ができるようになっています
・現時点で発売中止の予定はありません インターネットや書店でも購入が可能です
どんな本だったのか?
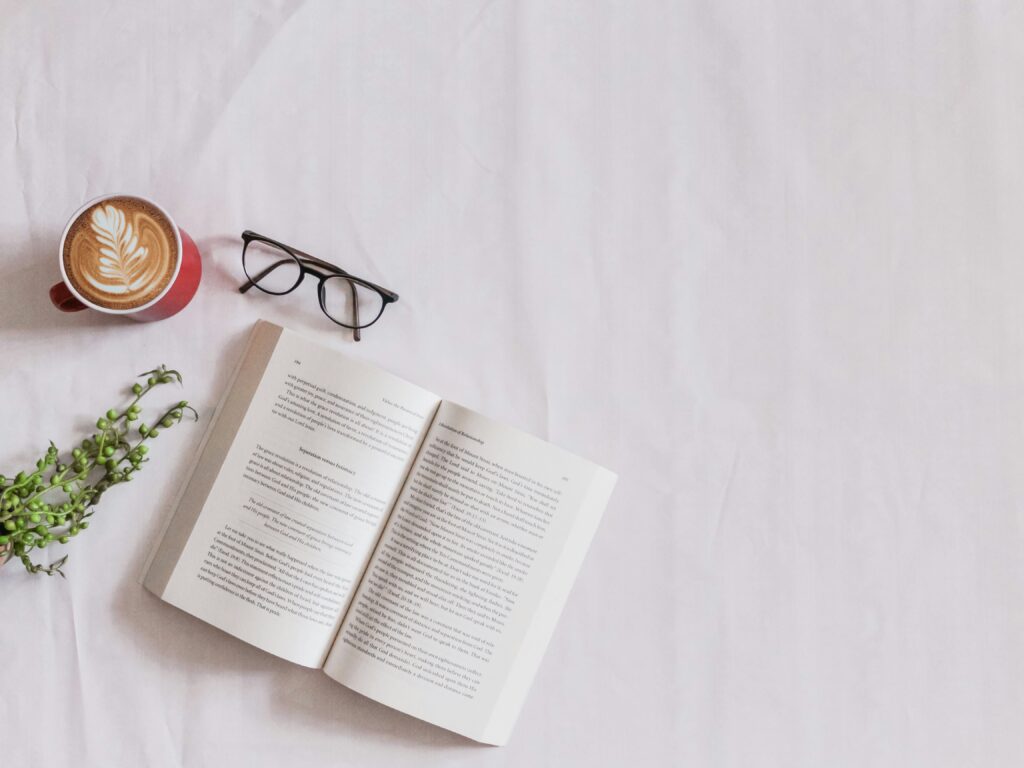
事の発端は、Xに投稿された本の告知からです。
『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』というタイトルで出版され、本の予約が開始されることが決まったという投稿でした。
本を書かれたのは、「スーパーカウンセラー」を名乗り、産業カウンセラーの資格をお持ちの方のようでした。
投稿された文章自体に炎上要素はなかったのですが、本の写真が添付されており、そこに掲載されていたタイトル、内容、挿絵などが大きく炎上することになりました。
問題視されたのは、大きく分けて以下の3つです。
①障害をはじめとする特性を持つ人たちを「困った人」と表現
②それぞれの特性を持つ人を動物に例えて表現
③「尻拭い」「はびこる」「戦わずして勝つ」「異臭を放ってもおかまいなし」などの誤解を招く恐れのあるワード
全体を通して、この本では以下の点が炎上の要因だったように思えます。
・言葉選びがよくなかったこと
・特性がある人を一括りにしてしまったこと
「困った人」という言葉は特性を持っている人を「迷惑」だと思っているように捉えられる可能性があります。また、「尻拭い」や「戦わずして勝つ」という言葉は、書き手側が優位に立っていると捉えられかねない書き方です。

特性を持っている人は、どちらかと言えば、困っている側です・・・
掲載されていた目次や他の内容を見ても、悲しくなるようなワードばかりでした。
正直、今のコンプライアンス的になぜ許されたのかが不思議ですし、この内容で通した出版社さんにも、不信感を抱いてしまいます。
なお、現時点で挿絵を担当したイラストレーターは、noteにて謝罪を行っており、「ラフイラストのフィードバックのタイミングで、キャラクターを動物に置き換える指示があった」ことを明かしています。
炎上要素となった4つの点

この本が炎上してしまった理由としては、いくつかの理由が挙げられます。
障害を持つ方を取り上げる際には、様々な部分で慎重になる必要がありますが、本書ではそういった配慮がほとんどされなかったことが原因だと考えられます。
1つずつ説明していきます。
①動物のイラストに特性のある人を合わせたこと
まずは、先にも述べましたが、特性のある人を動物に例えた点です。
本書では、それぞれの特性を持つ人を以下のように表現しています。
・ASDはナマケモノのイラストで「こだわり強めの過集中さん」
・ADHDはサルのイラストで「天真爛漫なひらめきダッシュさん」
・愛着障害はウサギのイラストで「愛着不足のかまってさん」
・トラウマ障害はヤギのイラストで「心に傷を抱えた敏感さん」
・世代ギャップはタヌキのイラストで「変化に対応できない価値観迷子さん」
・疾患はシマウマのイラストで「頑張りすぎて心が疲れたおやすみさん」
(疾患は自律神経失調症・うつ病。更年期障害・適応障害・不安障害・パニック障害を含めます)

どの言葉にもトゲが感じられるのは私だけでしょうか?
また、別ページのサルのイラストでは、バナナを食べながら「急がせないでね。ミスしちゃうよ〜」というセリフが描かれています。
サルやナマケモノ自体に罪はありませんが、名前や行動の特徴から、悪意を感じてしまう書き方なのは否めません。
イラストであっても、特性を動物に例えている時点でポジティブな捉え方はしにくいかと思います。
②誤解を招きやすい言葉選び
本全体にいえる特徴として、誤解を招きやすい言葉が多いことが挙げられます。
「困った人」「なぜ、いつも私があの人の尻拭いをさせられるのか?」という言葉は、まるで特定の人物のせいで「迷惑している」と言っているかのような書き方です。
他にも「戦わずして勝つ」と書かれたページがあるのですが、なぜ特性を持っている人とのやりとりが勝負ごとになっているのか?というのが正直な感想でした。
もちろん、度重なる対応で精神を疲弊してしまう人がいることは理解できます。
しかし当事者側の意見としては、勝ち負けを決めるのではなく、「どこがいけなかったのかを教える」「話し合う」といった方向性で書いてほしかったと感じてしまいました。
③一括りにするという危険性
以前、noteでも記事にしたことがあるのですが、私は「一括り」にする行為に憤りを感じます。
(ASDとは少し趣旨がズレてしまう内容ですが…)

障害や特性の程度は人によって様々です。
特に、ASDは「自閉スペクトラム(=連続体、範囲)症」とも言われているように、明確な境界線がありません。
しかし、この本では障害を持つ人たちを一括りにし、「困ったさん」と記載したうえで対処法を紹介しています。
もし、特性による生きづらさを抱えている人が、この本を見かけたら、どう感じるのでしょうか。
「困ったさん」と書かれ、対処法が記載されていたら、良い気はしないですよね。
場合によっては、該当する人を追い詰めてしまう可能性もあります。
そのような危険性があることを、考えられなかったのでしょうか。
適応障害になったことをきっかけに、ASDであることが判明した私からすると、この部分は特に許せない気持ちになりました。
④専門性の有無
この本の著者のプロフィールを拝見すると、「スーパーカウンセラー」「産業カウンセラー」との記載がありました。
調べたところ、スーパーカウンセラーというのは資格として存在しているわけではなく、自主的に名乗っているようでした。
本書ではADHDやASDなど、資格を持っている方でなければ診断を出せない障害の方についても記載がありますが、著者はそういった資格をお持ちではないようでした。
障害によって目立ちやすい特徴はありますが、資格がない状態で、該当する障害を持つ人たちの特徴や解決方法の記載をするのは、かなり危険です。
場合によっては、同業者の方にも被害が及ぶ可能性もあるのではないかと感じました。
当事者として感じた悲しさ

この本の存在を知った時に、まず私が感じたのは、「やっぱり発達障害者は困る存在なんだ」ということでした。
どの特性であれ、わざとではなく生じてしまった行動に対して「対処法」という言葉が使用されていることに、とても悲しい気持ちになりました。
障害を持つ人全員が「私は障害者だから周りに迷惑をかけてもいい」と思っているはずがありません。
私自身、自力でどうにかしようと思って行動し、迷惑をかけてしまった経験もあります。
その時に感じた罪悪感は、今でも忘れられません。
本書で確認できる中には、「〜たがる」「〜しがち」といった言葉もいくつか見受けられました。
特性と向き合いながら頑張って生きている人にとって、この言葉は受け入れ難いものです。
ましてや、この本を書いているのは、本来、発達障害を支援する立場の人です。
なお、一括りにされているのは、発達障害だけではありません。
本書では、うつ病や適応障害、更年期障害などにも「対処法」の記載があります。
著者は、自分を犠牲にして頑張り続け、体調を崩してしまった人も「困った人」に含めるつもりだったのでしょうか。
一部の特徴を切り抜いて「困ったさん」としてまとめることの危険性を自覚して欲しかったと思います。
こんな本だったら欲しかったという話

私は本の内容全てに問題があったとは思いません。
具体的な声かけ方法があるのはありがたいと思いますし、自分のメンタルを保つ方法などの記載があるのも、とても役立つと思いました。
さらに個人的な意見を書くとするならば、本書の特性に当てはまる人たちの「勘違いされやすい行動」や「特有の行動」などについて詳しく書かれていたら、私は迷わず手に取っていたように思います。
ASDに限ってかもしれませんが、日常生活を送る中で、世の中の「普通」がわからないことで悩んだ経験がある方は意外と多いです。
私自身、当たり前だと思っていたことが、世間では浮いて見えることだった、という苦い経験をしたことが何度もあります。
もし「世の中の普通マニュアル」のような本があったら、私は喉から手が出るほど欲しいです。
発達障害を専門とするカウンセラーとしての経験もおありの方なようなので、発達障害者の特徴を取り扱うのであれば、当人に気づかせる方向性の本も読んでみたかったなと思いました。
発達障害だけど、世の中に溶け込みたいという人はたくさんいると思います。

白い目で見られるあの感覚は、いくつになっても耐えられません・・・
センシティブな話題だからこその「配慮」が欲しかった

炎上してしまう要素はいくつか挙げられますが、一番は言葉選びだったように思います。
特定の人を下げるような言葉があったため、全体を通して「対象者」を排除しようとする書き方のように感じられてしまいました。
実際、記事では当事者からの厳しいコメントもかなり見受けられました。
言葉に配慮していれば、ここまで炎上することはなかったのではないでしょうか。
当事者としては心苦しい問題ではありましたが、世間のイメージや反応を直接肌で感じられる良い機会だったと思っています。




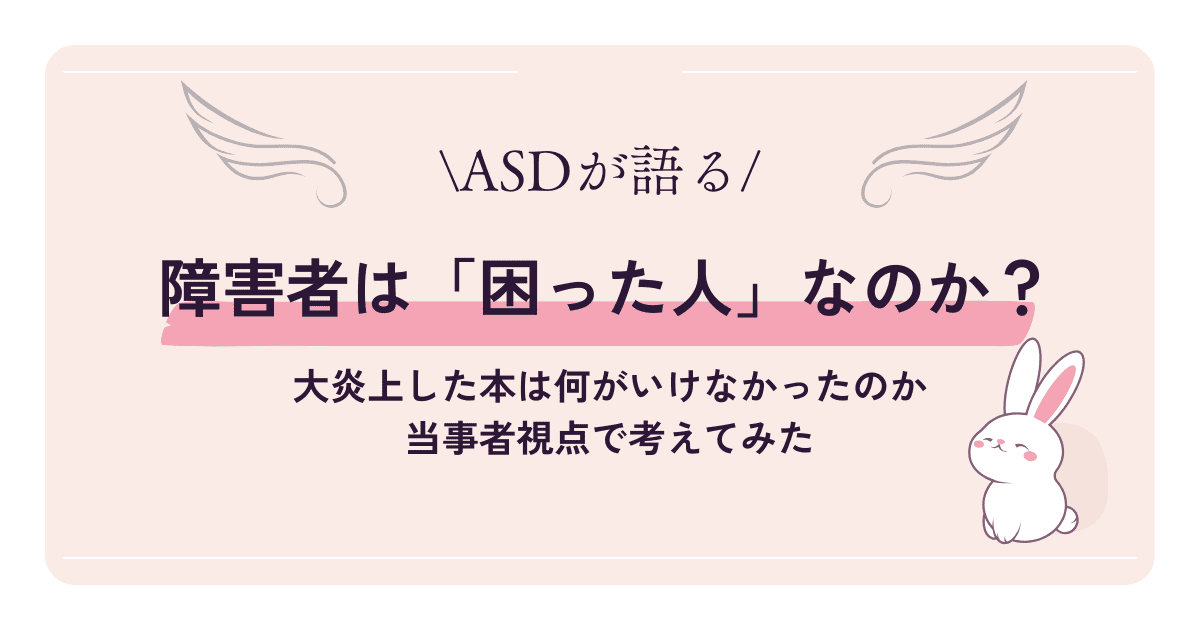

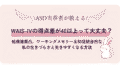
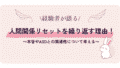
コメント