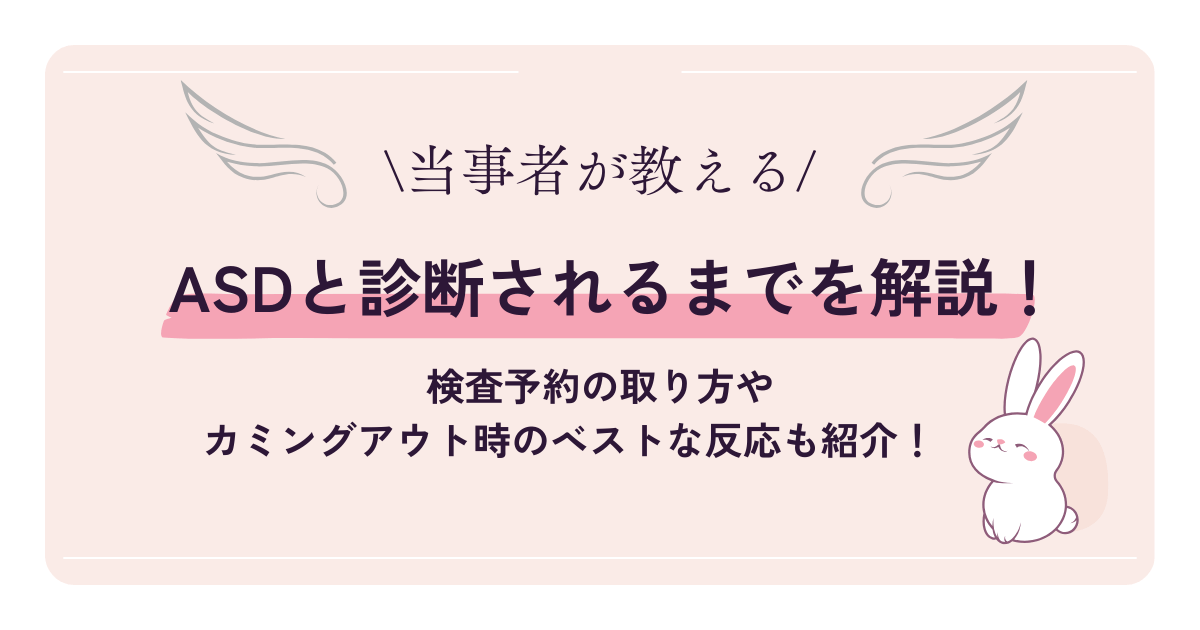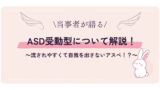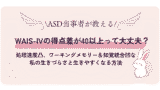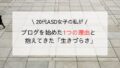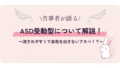こんにちは。栖山 依夜(すやま いよ)です。
私は2024年にASD(自閉スペクトラム・アスペルガー)の診断を受けました。
ASDの人は、人口に対して20~40人に1人いる可能性があると指摘されています。
そんなASDですが、診断については意外と知られていない部分が多くあります。
「ASDかもしれないが、どこで検査を受ければいいのかわからない」
「病院の予約って面倒くさそうで、なかなかできない・・・」
上記のような理由で、検査を受けることを諦めてしまう人も少なくありません。
私も「診断を受けたい」と思った際、何からすればよいのかわからず、困ってしまいました。
そこで、実際に検査を受けた経験のある私が、ASDと診断されるまでの流れについて紹介します。
当事者の視点で、「障害」を打ち明けた時に嬉しかった反応も紹介しているので、よければご覧ください。
・ASDの検査の受け方を知りたい
・自分はASDかもしれないと思っている
・身近にASDと診断された人や、そうかな?と思う人がいる
私がASDに真剣に向き合うことになったのは、通院していたメンタルクリニックでのカウンセリングがきっかけでした。
検査を受けて、良くも悪くも私は人生が大きく変わることになりました。診断された今だから言えることではありますが、もっと気軽に検査を受けていいのではないかと思います。
診断を受けるまでに気をつけること「3選」

診断を受けるまでにも、いくつかの注意が必要になります。
事前に対処できる問題がほとんどなので、下調べをしておくことが大切です。
ASD(自閉スペクトラム)には、大きく分けて、「積極奇異型」「受動型」「孤立型」の3タイプ、派生した「尊大型」「大仰型」2タイプの、計5タイプがあります。
タイプによって、言動や雰囲気が異なる場合も多いため、本文中の文章が必ずしも全てのASDに当てはまるというわけではないことを、ご了承いただければと思います。
私は「受動型」を自認していますが、これらは、医師から正式な診断が下るものではありません。
受動型についての記事は、こちらからお読みいただけます。
受けられる場所に注意!
発達障害と診断されるためには、以下の2つが必須条件です。
専門の医師がいること
心理検査ができる病院であること
簡易的なテストができる病院もありますが、専門医が在籍していない場合は、診断が貰えないので要注意。
発達障害の診断だけが欲しい!という方は、事前に確認が必要です。
「クリニック名 心理検査」で検索すると、検査の有無や具体的な持ち物、料金などが記載されているサイトもあるので、一度、調べてみることをおすすめします。
ちなみに、私が最初に通っていた病院は、発達障害の専門外でした。
てっきり、メンタルクリニックに行けば「発達障害の検査」ができると思い込んでいた私は、かなりショックを受けることとなりました・・・。

とにかく下調べが命です!!
病院を転院したい場合に注意!
現在通っている病院で検査ができずに転院をする場合は、通院中の主治医による診療情報提供書が必要になります。
よく、セカンドオピニオンをしたい旨を主治医に話すと、嫌味を言われたり、キレられたりするのではないか…?という心配の声を耳にしますが、全く問題ありません。
私の場合は、「カウンセリングをする中で、ASDかもしれないと思ったので、ちゃんと検査を受けたい」と言って、書類を書いてもらいました。
大事なのは気長に待つこと
そして、もう一つとても大切なことがあります。それは、とにかく待つことです。
メンタルクリニックは、全体的にスムーズに予約を取ることが難しいです。
私が現在、通っている病院に初めて検査の予約をした時は、2ヶ月以上待ちました。
基本的に「予約はすぐに取れないもの」と思っておくことが大切です。
自分の身体のこととなると、どうしても不安になったり、イライラしてしまったりするかと思いますが、焦らないことが大切です。
実際に受けた検査について

私はASDの検査を受ける際に、他の検査もいくつか受けました。
受けたのは以下の4つです。
①WAIS-Ⅲ(ウェイス)
②MSPA(エムスパ)
③PFスタディ(ピーエフスタディ)
④ADOS(エイドス)
発達障害を測るテストの中から、ADHDに関するものを抜いた検査が上記の4つになります。
私はADHD傾向はないと自己判断していたので、検査は受けませんでしたが、この部分は、医師としっかり話し合って決めてくださいね。
また、検査結果だけでASDやADHDという診断が下るのではなく、生育歴や現在の状況なども加えて総合的に判断します。
検査を受けたからといって、必ずASDと診断されることはないので、注意が必要です。
検査時は「いつも通り」の自分で大丈夫
個室に案内され、心理士さんと一対一の状態で行われます。
用意された道具を使ったり、問いに答えたり、心理士さんと話したりといったものが多いです。
雰囲気もとても和やかで、どちらかといえば、「検査」というより「面談」という言葉が合っているような気がしました。
検査によっては少し難しいと感じるものもありますが、言葉に詰まったり、手が止まったりしてしまっても全く問題ありません。
何よりも、わからないことがあれば、正直に聞くことが大切です。
自分の力を最大限に発揮できずに、検査を受けてしまうと、結果に影響が出てしまう可能性があるためです。
私も何度も質問してしまいましたが、優しく教えてくださいました。

わからないことは恥ずかしいことではないです!
所要時間は5時間以上かかることも!
検査によりますが、大体の所要時間は以下のようになります。
WAIS-Ⅲ(2時間)
MSPA(90分)
PFスタディ(20〜30分)
ADOS(1時間〜1時間半)
私の場合は、複数の検査を一気に受けたので、5時間ほどかかりました。
複数受ける場合は、途中で1時間程度のお昼休憩を挟むことになるので、近くに飲食店や喫茶店、コンビニなどがあるかどうかをチェックしておくことをおすすめします。
費用は「4万円」あれば安心?
検査によって、保険適用されるものとされないものがあります。
私が検査をした時は、ADOSのみが保険適応外でしたが、それだけでもかなりの出費になりました。
さらに検査予約料やフィードバック面接、検査報告書代などはプラス料金がかかります。
特に高いのが、「検査報告書」です。
1万円超えと決して安くないのですが、検査結果とフィードバックを手元に残しておけるので、とてもオススメです!
総額4万円ほどあれば問題ないと思いますが、事前に病院にいくらほどかかるかを聞いておくと安心できると思います。

クレジット未対応の病院もあるので注意してくださいね!
結果が出るまでは大体「1ヶ月」!
診断結果がわかるまでには、約1ヶ月かかりました。
私は検査報告書を希望していたので、担当心理士さんからの説明を受けました。
希望していない場合は、診察時に医師から結果を聞くことになると思います。
内容としては、自分の苦手とする部分や目立つ特性、考え方のクセなどを詳しく説明されました。
これらのフィードバックだけで1時間程度かかりました。
私の「生きづらさ」が明確になった検査結果は、こちらの記事で詳しく書いています!
私の場合は、心理士さんの見解では「ASD傾向はない」という診断でしたが、医師の見解で、最終的にASDと診断されました。
私のように、検査結果と医師の判断が異なる場合もあります。
最終的な診断をするのは医師なので、報告書の内容は「自分にはそういう傾向があるんだなぁ」程度に思っておく方がいいかもしれません。
ASDと診断されたら考えること

私は「ASD」と診断された時、特に驚くようなことはなかったのですが、診断後に少し困ったことがありました。それが、障害者手帳の申請と周囲へのカミングアウトです。
障害者手帳を申請するかどうかを決める
最初に悩むのが、障害者手帳の申請だと思います。
結論から言うと、私は手帳を取得してよかったと思っています。
障害者手帳は、基本的に取得しておいて損することはほとんどありません。
手帳を持っていると、公共交通機関の運賃が最大半額になったり、公共施設の料金が半額になったりといったサービスも受けることができます。
また、「手帳を持っていることが、就職に影響するのでは?」という声もよく耳にしますが、クローズ就労という方法もあります。
手帳の申請に関しては、1点だけ注意があります。
それは、「障がいの原因となった傷病について、初めて医師の診断を受けた日から6か月以上経過していること」が必須条件となることです。
6か月を過ぎていない場合は申請ができないので、しっかり確認してから申請してくださいね。
周囲へのカミングアウトはどうする?
これは私の経験上でのお話になりますが、無闇に話さないに限ります。
迷った場合は、まずは家族などの生活を共にする人だけに留めておきましょう。
そこから伝える人を吟味していく方法が一番安全です。
中には、発達障害に対してマイナスイメージを持っている人もいます。
特に、会社などでは、仕事が絡んでくるということもあり、カミングアウトをした途端に態度を変えてくる人もいるかもしれません。
言ってしまったあとに、やっぱりなかったことにする、はできません。
デリケートな問題になりますので、じっくり考えることを強くオススメします。
カミングアウトされた時のベストな反応、NG反応
次に、カミングアウトされた側についても考えてみます。
突然、「発達障害です」と打ち明けられたら、まず最初に浮かぶのは「どういう反応をしたらいいの?」ではないでしょうか。
「軽く流しても良いのか?」「サポートに回れば良いのか?」「労えば良いのか?」
いろいろ悩むと思いますが、当事者になってみて思うのは、
「そうなんだ」と軽く流してもらえるのが一番嬉しいということです。
私はASDの診断を受けた際、家族には電話で伝えました。
内心ドキドキしていたのですが、その時の家族の反応は、「そうなんや!」と拍子抜けするようなものでした。
“障害という言葉を重く受け止めず、ただただ目の前の事実を受け取ってくれる。“
この反応が、これから「障害者」として生きていく私にとっては、すごくありがたかったです。
逆にNGなのは、以下のような突き放す言葉です。
「配慮してアピール?」「で、結局どうしてほしいの?」
突然「障害者」と認定されて、困っているのは当事者も同じです。
嬉しい言葉と辛い言葉、どちらも経験した身としては、障害を持っていることを揶揄したり、できないと決めつけられたりすることが、一番辛い気持ちになります。
普段通り接してくれることが、一番の安心になります。
「スペクトラム」ということを忘れないで
最後に、自閉スペクトラムという言葉について説明して、この記事を締めようと思います。
「自閉スペクトラム症」という言葉の「スペクトラム」という部分。
この「スペクトラム」には、「連続体」「範囲」という意味があります。
簡単にいうと、境界線や範囲が明確ではない状態がずっと続いているということです。
つまり、「スペクトラム」は、どちらか1つという答えがあるのではなく、傾向が強いのか、弱いのか、といった捉え方が近いのです。
もし、これを読んでくださっているあなたや、あなたの身近な人が「ASD」だったとしても、その傾向の強さは人それぞれです。
発達障害だからダメなんてことは絶対にありません。
そのことを、どうか忘れないでいてほしいと思います。